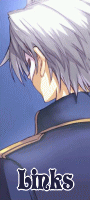| .......................................................................................................................................................................................................................................... |
| これはTWの原作小説『ルーンの子供たち DEMONIC』の日本版完結を記念して、そして何よりマックス・カルディの未来を思ってHursaが制作した(一応)オリジナルの小説です。 マックス・カルディが目覚める未来のできごとで、できる範囲で補足はしたつもりですが、原作をご存知ないとかなり訳の判らない話になっています。 その上きわめて自己満足のために書いた話なので、他の方々にご満足いただけるかどうか甚だ疑問でもあります。 が、わたしなりの救いを書いたつもりですので、カルディの幸せを願ってらっしゃる方がいれば、読んでいただけると、少し何かが変わる……かもしれませんし何も変わらないかもしれませんが、わたしのカルディへの愛だけはご理解いただけるかもしれません。 Hursa |
| .......................................................................................................................................................................................................................................... |
| 少年は久しく忘れていた肉体の痛みに、長い長い眠りから目を覚ました。頬に鈍く残る感触は、彼の忘却を知らない記憶に刻まれたどの痛みよりも新鮮だ。 そう、たとえ彼が決して褪せることのない苦痛に満ちた記憶を重ね続けるとしても、現実の鮮烈さは容易く過去を凌駕する。 少年は小さなうめき声をあげて、ゆっくりと両目を開いた。 その黒い瞳に映ったのは、目の覚めるような青空を背負って上から覗き込んでいる、彼よりもずっと幼い少年のあどけない、しかし、どこか生意気そうな顔だった。 「マック君……」 彼がそう呟いたとたん、再び頬に痛みが走る。眉根を寄せ、視線を痛みの源へ流すと、少年が彼の頬を小さな手でつねりあげているのが見えた。 「痛いよ、マック君」 「マック君って誰だよ?」 弱々しい彼の抗議に、少年は見た目の年齢よりもずっと大人びた口調でそう応じた。それからぱっと手を広げてつねっていた頬を離し、「死んでるかと思ったのに、生きていたのか」とどこか不満そうに口をとがらせる。 「生きているなら、こんなところでまぎらわしく倒れているなよな」 そう言って小さな少年は、横たわっている彼の頭の傍に腕を組んで勢いよく座り込んだ。その拍子に小さな白い花びらがいくつも地面から舞い上がり、雪のように彼の顔の上に降りかかる。それと同時に暖かな春を思わせるやわらかな花の香りが鼻腔をくすぐった。 彼はひりひりと痛む頬に手を伸ばし、傍らの少年へと目を向けたが、その時になって初めて、『マック君』がいつもかけているはずの眼鏡が、少年の子供らしい小さな鼻の上にはないことに気がついた。顔立ちや雰囲気こそ似ていたが、よく見ると髪の色も、思い出の中にある友達のものよりもずっと赤い。 「マック君、眼鏡をどうしたの? その髪は? それにどうしてそんなに小さくなってしまったの? ぼくの記憶に間違いがなければ、おまえはぼくよりも年下だったけど、十も違わなかったはずだ」 顔に乗ったままの花びらを払うことも忘れて彼が訊くと、少年は苛立たしそうに、 「だからマック君って誰だよ」 と精一杯の怖い顔で睨んできた。もちろん子供のそんな表情など怖くはなかったが、彼は地面に横たわったまま凍りついたように固まってしまった――というのも、何故か少年の口にした言葉が頬の痛みさえ忘れさせるほどに心をえぐったからだ。 彼はふいに身体を起こし、その勢いに驚いて目を丸くしている少年に向かって叫ぶように言った。 「マック君はマック君だよ。どうしてそんなことを言うの? 確かにおまえにとって『ぼく』は友達じゃなかったのかもしれないけど、マック君がマック君だということまで否定しないでよ。それとも自分の名前を忘れてしまったの? ぼくのことも? ぼくは……」 彼はそこまで言って、はたと口をつぐんだ。「ぼくはジョシュアだ」と名乗りかけて、その名前がもう彼自身にふさわしくないものであることを思い出したのだ。 「ぼくの名前を知ってる……?」 顔を伏せ、消え入りそうな声で彼が言うと、少年はにべもなく「知るか」と答えた。 「おれはおまえなんて知らないし、『マック君』なんていう間の抜けた名前でもない」 「じゃあ、なんていう名前なの?」 この問いに少年は、すぐには答えなかった。不自然に訪れた沈黙をいぶかり、彼がそろりと顔を上げると、少年は実に不本意だといった表情をしてみせる。そして、「マックス」とやがて不機嫌そうに答えた。 「本当に?」 思わず彼はそう訊き返したが、少年の様子からして嘘であるはずはなかった。 「やっぱり『マック君』じゃないか」 「ちょっと似てるだけだ!」 半ば呆然として言う彼に、少年は顔を真っ赤にして怒りながらそうはねつける。 その表情は、彼の知っている友達にとてもよく似ていた。腐れ牧場と呼ばれていた地で共に幼少時代を過ごした幼馴染のマック君――マキシミンに。 しかし、マキシミンは彼とあまり年の変わらない少年だったはずだ。「ぼくの記憶が正しければ」と彼は先ほど言ったが、彼が記憶違いをすることなどあるはずがない。悪魔に祝福された幸運とも不運とも判らない天賦の才を持つ彼は、人に許された『忘却』の救いから見放された『デモニック』だったからだ。 そしてそうである以上、彼の記憶通り、今の彼がすらりとした長身を持つ十代後半の少年になっているのと同じように、マキシミンも腐れ牧場の小さな子供ではなくなっているはずだった。 ――そうだ、ぼくは成長したマック君に会ったじゃないか。ネニャフル学院で……。 心の内でそう呟いた瞬間、彼の頭は長かった眠りの余韻からすっかり醒め、混乱していた記憶が整然と並び、たとえ一瞬でも思い出すのがつらい、眠る前の過去が脳裏に瞬時にしてすべてよみがえった。 ジョシュア・フォン・アルニムの身体的能力と、一時期までの記憶をそっくりそのまま持って生まれた人形。作られた存在。本物のジョシュア・フォン・アルニムが選ばなかった道を歩むことになった、友に選ばれずその時代から切り離された影――それが彼、正体を隠した仮面の俳優の名を与えられた『マックス・カルディ』だった。 本物のジョシュアがいる以上、もう一人のジョシュアとして同じ時代を生きていくことができなくなった彼――カルディは、三十年後か五十年後、それとも百年後かに目を覚まし、彼自身の時代を生きていくことになっていたのだ。彼のことを知る人がいなくなった孤独な時代を。 「なんで急に泣き出すんだよ」 目の前の子供――今の彼と同じ名前を持つマックス少年があげた狼狽の声で我に返り、カルディは痛む頬の上をいたわるように滑り落ちていくものが涙であることにようやく気が付いた。 視界がぼやけて、少年の顔がよく判らない。ただ、思い出の中にあるものとは少し違う声だけがはっきりと聞こえた。 「おれより大人のくせに泣くなよ。そんなに強くつねってないぞ」 痛いのはもう、頬ではない。涙が出るのは、長い長い眠りの中でさえ常にカルディに付きまとっていた心の痛みが戻ったからだ。 彼は頬をつねられたことによる肉体の痛みで目覚めたが、眠り続けている間に見ていた記憶と夢の中ではずっと、その心の痛みにさいなまれていた。 選ばれなかった自分。本物ではなかった自分。自分のものだと信じていた友情は、精巧に作られた記憶に過ぎなかった。そして彼自身もまた、記憶のように作られた偽者でしかなかったのだ。 本物にはなれない。ジョシュアの友達は、本物であるジョシュアのものだ。人形である自分がそれを自分のものだと主張する権利はない。それならジョシュアは彼に対して、そもそもその記憶はぼくのものだと言わねばならないだろう。 だがもしジョシュア自身が、人形になることを望んでいたらどうだったろう? 小公爵ジョシュア・フォン・アルニムとしてではなく、俳優マックス・カルディとして生きることを選んでいたとしたら? そしてカルディがジョシュアになっていたとしたら――自分が本物のジョシュアだと名乗るカルディを、マキシミンは幼馴染のジョシュアだと信じたのだろうか。 判らない。あの聡い友人なら気づいたのかもしれない、たとえ二人が違う存在でありながら本当にまったく同じ人間だったとしても。 しかし、あるいは気づかなかったのかもしれないのだ、食い違う記憶をカルディが補完しさえしていれば。 だが、マキシミンを責めることはできなかった。ただ声をあげて泣きながら、どうしてぼくじゃないのかと叫びたかった。 記憶は記憶だ。捏造されたわけではない。確かにあったものが一つ、そのままの形で増えただけなのだ。ジョシュアと呼ばれていた少年と、マキシミンという少年が、幼い頃に共に過ごし、一つの思い出を作ったことは確かで、忘れがたき記憶となったそれはジョシュアの頭の中にも、マキシミンの頭の中にも存在し、そのことが『確かに存在した過去』だと証明している。そしてその記憶がカルディにもあるという、ただそれだけのことだ。 それだけのことなのに決定的に違ってしまったのは、マキシミンが同じ友達を二人も望まなかったから。そして望まれなかったのは、人形であるカルディだったのだ。 ――ぼくにとっては、あの記憶は嘘ではないのに。おまえにとってもそうであるように。 それでも彼は、本物であるジョシュアと同じ時代に生きることはできなかった。それで良かったのだろう、いや、きっとそれしかなったのだろうと思う。だが、そう判っていても胸をえぐる痛みだけは決して去ることはなかった。 悲しい。切ない。淋しい。 ただひたすら、涙だけが時の代わりに流れ去った。その間にどれほどの時間が彼の上を素通りしていったのかも判らない。目の前にいる少年はマキシミンではなく、彼のことを知らない人間の一人だということだけが、残酷なほど確かなことだ。 「ぼくは一人なんだ。目を覚ましたらぼくが知っている人も、ぼくを知っている人も、誰もいない。それが悲しいんだ」 ようやくカルディがそう言って服の袖で涙を拭うと、少し鮮明になった視界の中でマックス少年が気まずそうに「なんだそれは」とぼやいた。 「おれなんか生まれた時から一人だぞ。知らない大人ばっかりで親なんていなかったし、もちろん友達だって」 それなのに何を贅沢な、と言わんばかりに彼は小さな肩をいからせ、カルディを睨む。 「でもおれは自分で家族と友達を作ってきた。泣いてたって誰も助けてくれないんだぞ」 その言葉は、まるでマキシミンの口から出たもののようだった。彼がここにいたら、きっと同じことを言ったに違いない。彼は特有の皮肉めいた口調で真実を言う。そしてそれはいつだって、ぶっきらぼうながら得がたい励ましとなったのだ。 「君、本当はマキシミンという名前じゃないの?」 ついそう訊くと、また少年は声を荒げて怒り出した。 「おれはマックスだって言ってるだろ! そんな運の悪そうな名前じゃない」 「それ、当たってるかも」 そう言ってカルディはかすかに笑った。マキシミンと別れ、眠りについてからは彼がどんな人生を送ったかなど知らなかったが、記憶の中の彼は不景気そうなしかめ面をしていることが多い。そのことが少しだけおかしかった。 「君にかかるとどんな名前でもけちをつけられそうだな。ティチエルというのはどう?」 「女の名前じゃないのか、それ? なんかお節介そうだ」 「じゃあ、ボリスは?」 「氷みたいな名前だ」 「ヒスファニエ」 「海賊みたい」 「ぼくの名前は?」 最後に飛び出したその問いにマックス少年は「またか」というような顔をしてみせた。 「さっきも言っただろ。おれが知るかよ」 ふん、と鼻を鳴らしてそっぽを向いた少年に、カルディは先ほどよりもはっきりと笑いかける。そして、落ち着いた声で自分の名前を告げた。 「ぼくもマックスだよ。マックス・カルディって言うんだ」 「嘘だ」 マックス少年の即答にカルディは今度は苦笑を浮かべ、「本当だよ」と言って彼を振り向かせた。 「知らないかな? これでもブルー・コーラルで一時有名になった俳優なんだけど」 「知らない」 「……ジョシュアは?」 「知らない。それより、本当にお前の名前もマックスなのか?」 「そうだよ。……今はね」 カルディは一瞬だけ苦い表情で沈黙をはさんだが、そのことにマックス少年は気づかなかったようだった。何事か考えているような顔であらぬ方を見ながら、白い花の茎をいじっている。カルディもそれをぼんやりと見守っていたが、やがて痛みのひいた頬に手を当ててぽつりと口を開いた。 「ねえ、どうしてぼくをつねったの?」 「死んでたら持ち物をいただこうと思ったから。生きてる奴から物を取ったら泥棒だけど、死んでる奴から取っても拾ったのと同じだろ。だから確かめようと思ったんだ」 彼の知っている『マック君』なら、必要とあらば『泥棒』と呼ばれてもそれをやっただろうが、しかし、マックス少年の屁理屈はいかにも『マック君』らしかった。その不思議な共通点はカルディの胸を切なくひっかいたが、同時に懐かしさで心を優しく満たしていく。 「それじゃあ、生きていると知って、その上ぼくが人違いをしていると判っていながら、どうしてそこに座ったの? ぼくが生きていたら用はなかったはずじゃないか」 「おれがどこにいつ座ろうが、おれの勝手だろう」 「でも何か理由があったと思うんだけど」 歯切れよく答えていたマックス少年も、これにはしばらくの沈黙を要した。 「おれに少しだけ似た名前をお前が呼んだからだ」 ようやくそう答えた彼の顔は、今までよりもさらに機嫌が悪そうだった。そんな表情からは、他に理由があったのかどうか読み取れない。 「おまえ、こんなところで何をしてたんだ? 死体ごっこが好きなのか?」 不機嫌そうな口調のまま、マックス少年は唐突にそう尋ねてきた。その口ぶりにまたカルディは笑いながら、首を振ってみせる。 「時が来るまでずっと眠っていたんだ。結界の中でね」 「結界?」 「外の世界からぼくを切り離しておくためのものだよ。どれくらいの時間がたったのかはぼくにも判らない。でも、とても長く、長く……本当に長く、悲しい眠りだった」 しかし、今はその悲しみに耐えられないほどではなかった。彼の時代がやってきたのだ。少年の言う通り、泣いていても、誰も助けてはくれない。それならば行動するしかないではないか。 「ぼくは行かなくちゃ。やりたいことがたくさんあるんだ」 腕には未だ消滅を意味する痛々しい痕跡がある。それを治せる者を探さなければならなかった。もうじっと死を待つつもりはない。すべては始まったばかりなのだから。 もちろん、また俳優として舞台にも立ちたかった。 「おまえ一人で大丈夫なのか? どこに行くのか知らないけど、おまえはすごく頼りなさそうだぞ」 まるで年下の弟を心配するような調子でマックス少年が言うと、カルディは少し意地悪を言ってみたくなってこう答えた。 「平気だよ。生きていく方法は、君が昔教えてくれた」 「おれは教えてない。『マック君』だろ」 「そう、君によく似た『マック君』が教えてくれた。だから大丈夫」 それを聞いてマックス少年は、ちぇ、と小さく舌打ちをする。 一方カルディはようやく一つ勝ったというような気になり、まるで本当にマック君と話しているみたいだなと内心で苦笑した。それから小さな少年に向かって右手を差し伸ばす。 「君はぼくの新しい、そして最初の友達だよ、マックス」 「……そう言うなら友達になってやってもいいけど、おれもお前のことをマックスと呼ぶのか?」 おずおずと手を握り返してきた少年にカルディは、晴れやかな笑顔を返してこう答えた。 「カルディでいいよ」 そう、今はもうジョシュアではなく、カルディでいい。きっとマックスに会わなければ、彼はこんな真っ直ぐな明るい気持ちで、ジョシュアのいないかもしれない時代にマックス・カルディと名乗ることはできなかっただろう。今は握手を交わしてる少年との不思議な縁さえ感じられる『マックス・カルディ』と名乗れることが誇らしかった。 ――やり残したことをやりに行こう。ジョシュア・フォン・アルニムのためではなく自分のために、やりたいことは何だって。 昔の友達は傍にいない。それはやはり今でもひどく悲しいけれど、それでも、その代わり、彼は自由だ。もう仮面も必要ない。耐え難い痛みを代償に手に入れた自由は、それほどの価値があるものなのだ。 それにマックスが言っていたではないか、自分は生まれた時から一人だったと。それは真実だ。誰も初めから友達を持って生まれてはこない。彼はマックス・カルディとして生まれ変わったのだ、何も持たず、ゼロから始めるべきだった。そしてゼロとは、どんな数字にでもなれる可能性を秘めている。無限の可能性だけが、ゼロにはある。 「ところで、今は何年の何月……あ、何年かなんてどうでもいいや。目が覚めたということは、ぼくの時代ということなんだから」 カルディはそう言って笑うと、服についた花びらをはたき落としながら立ち上がり、改めて『友』に訊き直した。 「今は春でいいのかな? それとも秋? それくらいは知っておかないと、次に来るのが夏だと思って油断しているところに冬が来たら大変だ」 「花が咲いてるんだから春に決まってるだろ」 バカなことを言うなよとばかりに呆れながらマックスは答える。それにカルディは小さく肩をすくめてみせた。 「花は春だけのものじゃないよ。冬に花が咲くものもあるんだから。アーモンドの木みたいにね」 「冬に? 春を待たないなんて、やけに気の早い木なんだな」 カルディがうなずいた。 「うん。でも、とてもきれいな花が咲くんだ」 Fin. clap? |
| .......................................................................................................................................................................................................................................... |
| ▼とても長い蛇足 ここからは蛇足です。つたない小説を読んで下さり、納得いかないぞ思われた方で、言い訳を聞いてやろうじゃないかと思われた方にはご覧いただけると良いかもしれません。 ただ、それを見ていただいたからといって必ずしもご満足いただけるとは限りません――というのも、この小説はあくまでHursa個人がカルディのために流さねばならない涙の処理場として書いたものだからです。 つまり自己満足に過ぎないのであまり期待はなさらないで下さい、ということであります。 ただ、重ねて言いますがこれは本当に蛇足です。 元来わたしは自分の書いた話にあれこれ説明を付けるのは好みません。著者の意図がどうであれ、書かれた話の解釈はそれを読んだ人が自由に持つべきだと思っているからです。 野暮な国語の試験のように、それが間違っているとか正しいとか言うつもりはありません。 ですから、本来ならご自身の解釈を一番大切にしていただきたいのですが、この小説がすべてわたし自身の作り上げた設定ではないので、原作とのかかわりを説明する手段として、書いておきたいと思います。 前置きが長くなりましたが、そんなものでもよろしければどうぞご覧下さい。 マックス少年について 彼は一応オリジナルのキャラクタになります。 彼がマキシミンに似ているのは、カルディになぐさめのようなものをあげたかったからです。それならマキシミンと同じ年齢で同じ容姿にすれば良いじゃないかと思われるかもしれませんが、マキシミンという人間が一人である以上、誰にも代わりはできません。 また、友達を失ったからといってその人の「代わり」をカルディには作って欲しくなかったのです。誰かの代わりなんて、彼はうんざりでしょうから。 だから髪の色が少し違う、眼鏡をかけていない別の、しかしよく似た少年になりました。 最後の方でカルディはマックス少年のことを「マック君」と言っていますが、二人称はマック君に使っていた「おまえ」ではなく「君」を使っています。ただ意地悪のつもりで「マック君」と言っただけで、これはきちんと彼がマックス少年とマキシミンを別の人間だと考えている、という表現のつもりで、書き分けました。 マックス少年を子供にした理由は、カルディが新しい時代に目覚めた=生まれた時に、子供の頃にマキシミンがジョシュアに生きる術を教えたように、当時のマキシミンと同じ立場の人にカルディの背中を押して欲しかったからです。 ただ、彼がマキシミンの血筋の人かどうかは判りません。そうであってもいいし、そうでなくてもいいと思っています。 彼がマキシミンという名前を聞いた時の反応は、知り合いをバカにしているようにも、まったく知らない名前の印象を適当に口にしたようにもとれる風にしたつもりです……が、そこはあまりつっこまないでいただけると嬉しいです。 彼自身の「マックス」という名前は、もちろんマックス・カルディからとってつけました。マキシミンと繋がりがあるようにもないようにも思える名前にしたかったのと、何か……カルディと新しい時代とを繋ぐ共通点のようなものを彼に贈りたかったからです。 そんなことばかり言っていますが、それくらいわたしはカルディの幸せを願っています。 あと、最初はリチェによく似た女の子も書いていたのですが、よく考えたらカルディはリチェとほとんど面識がなかったはずなので、女の子と男の子を出したかったのに、とちょっとがっかりしました。 そんなわけで、せめて髪の色だけでもリチェの名残を、と思いマックス少年は赤髪になっています。リチェとマキシミンの子供だと想定しているわけではありません。 結界について 結界は洞窟に張られたはずなのに、カルディが目覚めたのは野原のど真ん中で洞窟はどこにもありません。本当なら洞窟の中で目覚めるべきなのですが、どうしても明るい日差しの中で、誰かに傍にいてもらいたかったので、洞窟の外にしました。 カルディの時代が来て目覚めた時、暗い洞窟の闇ではなく暖かな太陽の光に照らされるように、誰かが何かしかけをしたのだとでも思っていただければ幸いです。それくらいの無理は、何とか誰か(たぶんジョシュア)にやってもらいたいなと思いました。 原作と同じ終わり方について これこそ蛇足ですが、それを承知であえて申しますと、わたしはどうしても「カルディもジョシュアである」と証明したかったのです。 それでカルディが知らないはずのジョシュアのせりふを言わせました。本質は同じ人間だということです。 カルディはもはやジョシュアではありませんが、確かにかつてジョシュアであった人です。彼は生まれたばかりで、これからどんどんジョシュアとは変わっていくでしょう。ジョシュアが見たいと言った、別の姿になります。 しかし、それと同時に、彼は確かにジョシュアであると、きちんと証明しておきたかったのです。 ちょっとだけマキシミンへの復讐でもあります。わたしはマキシミンの出した結論を責めるつもりはありません。でも、彼の結論を認めるからこそカルディが不憫でならないのです。だからどうしても、彼もジョシュアなんだと証明しておきたかったのでした。 もう一本蛇の足 何故わたしがこれほどまでにカルディに肩入れするのかと言うと、わたしに彼と同じような気持ちを抱かせ続けた双子の兄弟がいるからです。 今は別々に暮らしていますが、その人といる時は「自己主張」の毎日でした。 「二人で一人」のように見られるのも、「どちらでも構わない」と思われるのも、もう一人の「代わり」だとされるのもわたしは大嫌いでした。わたしはわたしであるところの自分を見てもらいたかったのです。確かに似ているけど、違う人間なんだから一人の人間として見て欲しい、と思い続けた者です。 だから、改めてマキシミンと友達になることだってできるはずだと考えたカルディの気持ちがよく判ります。それだけに、選ばれなかったことのやるせなさも判る気がしました。彼のジョシュアに対する思いも。 そうしたらカルディの明るい未来の話を書きたくて仕方がなくなったのです。 わたしにはわたし自身の明るい未来を都合よく作ることはできませんが、彼のことは書くことができますから。 長々と書いてしまいましたが、ここまで読んで下さった方がもしいらっしゃるなら、心からお礼を申し上げます。 完全に自分へのなぐさめのために書いた話ですが、少しでもこれを読んで下さった方の中のカルディが幸せになれば、それ以上の喜びはありません。 ありがとうございました。 マックス・カルディの新しい人生に輝かしい未来のあらんことを。 |
| .......................................................................................................................................................................................................................................... |
ランジエ&ジョシュア誕主催サイト様: HisTales ホーム: |
| .......................................................................................................................................................................................................................................... |