| .......................................................................................................................................................................................................................................... |
| このお話は今年のジョシュアの誕生日イベントを元に、Hursaが偏りまくった愛情で解釈し、小説化したものです。 一部、シーンを削除したり、逆にイベントにはなかったシーンやセリフを追加したりもしています。イベントの内容について、解釈は人それぞれだと思うので、これもいちジョシュアファンの解釈の一つと思って読んでいただければ幸いです。 Hursa |
| .......................................................................................................................................................................................................................................... |
| 冬の終わりを感じさせる柔らかな風が穏やかに髪を巻き上げるのを心地よく感じながら、ジョシュアは誰もいないテラスで一人、ぼんやりと眼前に広がる見慣れた風景を眺めていた。階下では彼の誕生日を祝うべく訪れた名だたる諸侯の型通りの祝辞やお世辞も出つくし、着飾った貴婦人のごとくうわべだけは上手に飾った世間話がくり広げられていることだろう。 ジョシュアは今日の誕生パーティの主役ではあったが、仮面のように愛想のいい笑顔をはりつけて、リボンをほどいてみる気にもなれないたくさんの贈り物を受け取るという義務が一通り終わると、すぐにこんな退屈なパーティには飽きてしまった。彼のために贈られたはずの物でさえ、実のところジョシュアにとっては何の意味もないことを彼は知っている――というのも、綺麗に包装されたきらびやかな贈り物は、「どこそこの誰それから贈られた」という事実だけが大事なのであり、中身など問題ではないからだ。 「あれはオレのために贈られた物じゃなく、公爵である父への贈り物だろう。」 ジョシュアは誕生日が毎年律儀にやってきて、欲しくもない贈り物を笑顔で受け取る義務を課せられるたびに、そんなことを考えてきた。ずっとずっと、幼い子供の頃からだ。 「次期公爵としてのオレではなく、個人としてのオレに贈り物をしようなんて思う人はきっと、今日来た人たちの中に一人だっていやしないだろうな。」 ジョシュアは皮肉っぽく心の中でそう呟いて、風で乱れた髪を直そうと無造作に手を伸ばした。柔らかな灰色の髪をすくった指が、小さな髪飾りに触れる。そこで彼は、今朝ふと思い立って開いた、普段は閉めたままのひきだしの一つから見つけた髪飾りを、髪につけていたことを思い出した。 それは四つ葉のクローバーの形をしており、一般に「幸せクローバー」と呼ばれている、大切な人へ幸せや幸運を祈って贈る物だ。決して高価な物ではないから、今日屋敷へやってきたような貴族たちは彼にそんな物を持参することはないが、彼らが忘れている「贈り物」にはもっとも必要な真心が、それにはこめられている。 しかし、ジョシュアはどうしてもそれをくれた相手のことを思い出せずにいた。まるで誕生日がめぐってくるまで記憶に鍵をかけていたかのように、彼はその髪飾りのことを今朝まで忘れてしまっていたし、日付が変わり、太陽が昇って、何気なくひきだしを開いた途端にすべての鍵がはずれたとでもいうようによみがえった思い出の中にさえ、プレゼントの贈り主の姿はなかったのである。 本来、ジョシュアが何かを忘れてしまうということは決してない。一時的に記憶の片隅に押しやられることはあっても、それを失うという「忘却」は彼にもっとも縁遠いものであるはずなのだ。 「それなのに、オレが『忘れてしまうこと』があるなんて。」 彼は不思議で仕方がないといった様子で言いながら目をつむり、封印されていた記憶を頭の中で再びよみがえらせた。 はじめに思い出すのは、明るい緑の木々や色とりどりの草花に囲まれた見慣れない小さな広場と、暖かな日の差す、しかし、どこか寂しさをたたえた静寂。そして、そんな美しい光景の中にいながら、一人でたたずんでいることが不安なのか、それとも何故自分がそこにいるのか判らないことによる困惑なのか、胸にざわざわと不穏な波をたてている焦燥のようなもの。小さな子供の姿で、ジョシュアはそんな奇妙な気分を抱えながら、綺麗な広場に立っていた。 「一体ここはどこなんだろう? どうしてぼくは一人でこんな所にいるんだろう……?」 そんなことを呟きながら周囲を見回すと、たくさんの贈り物と、子供の姿をした今のジョシュアの背たけを軽く超える巨大なケーキが視界に飛び込んでくる。それと同時に、このプレゼントの山は自分の誕生日を祝って贈られたものであり、ここを訪れてくれた人にケーキを振る舞うのが今の自分の役目なのだと彼は漠然と悟った。気がつけば彼にお祝いの言葉を言おうとたくさんの人々が大きなプレゼントを手に並んでいる。 ジョシュアはいつものように柔らかな表情を浮かべてお礼を言いながら、彼らに一つ一つケーキを手渡していった。 そんな中でただ一人、何度も彼に話しかけてきた者がいる。二百八十二番目に彼の下を訪れたその人は、どこからやってきたのか判らず、またどうやってどこへ帰っていくのかも判らない人々がすっかり立ち去り、ケーキがあらかた片付いても、帰るそぶりを見せることなく気さくに声をかけてきた。 しかも、ありきたりなお祝いの言葉やお世辞を言うわけではなく、ただ彼に何か話してほしそうにしているのだ。親しくもない相手に何を言えばいいのか判らなかったジョシュアは、最後には歌でも歌ってくれとせがまれ、困惑顔でこう答えた。 「この綺麗で寂しい場所で、あなただけのための歌を? ……ねえ、ぼくから何の話が聞きたいの? ぼくの所に来て自分の話を勝手に喋る人は多いけど、あなたみたいにぼくに何でもいいから話してみてっていう人は珍しいよ。こういうのって、普通『面倒くさい』って言わない?」 それは遠回しの拒絶だったのだが、それでも相手は彼と言葉を交わすことを望み、人気のなくなった広場で、やがてすることもなくなり、仕方なく手近にあった花で冠を作りながら見知らぬ場所で帰る方法も判らず途方に暮れるジョシュアの傍らに、じっと居続けた。どれくらいの時間が経ったのか、彼にも判らない。ただ、決して短くはない時間をその人はジョシュアのために費やしたことだけは判った。そのことに気付くと、ようやく、相手が暇つぶしにおしゃべりをしていたわけでも、何かが欲しくてはりついていたわけでもなく、ひたすら自分に好意を示してくれていたのだとジョシュアは悟る。そのためだけに相手がずっとここにいたのだと知って、ジョシュアは少なからず混乱した。何故なら、それは彼にとって理解しがたいことであったからだ。 「あなたは願いがある? あなたは失いたくないものがある? ぼくにはそういうものが一つもないんだ。だから、誰かのことを特別に思うというのは無理だし、その人のためにすごく努力することもできないんだ。だけどあなたは……。」 そこで一度口をつぐみ、しばらく何事か考えているそぶりを見せたあと、 「あなたは真面目な人なんだね。ぼくにはできないな。ぼくはあなたに冷たいことも言ったから、そのうち呆れて帰ってしまうと思ったのに……すごいよ。これって褒め言葉だよ。真面目な褒め言葉。気を悪くしないでね。ただ、あなたは忍耐強くて、とても良い人だと言いたかったんだ。本当にすごいよ。」 とうとうジョシュアは自分からそう口にして、相手に柔らかな笑顔を向けた。そこにはもう混乱の色はなく、歳には相応しくないほどの大人びた表情が浮かんでいる。 「『大切に思う』とか『失いたくない』とか、そんなことを言ったって変わらないじゃない? 起こったことは既に起こってしまったことだから仕方ないでしょ?」 ジョシュアは相手の反応をうかがうようにそこで言葉を切ったが、「子供がそんなことを言うな。」と怒り出す気配がないのを見て、声をあげて笑った。 「こんなことを言うぼくを叱る人もいるのに、あなたはそうじゃない。本当に変わった人だね。もしかして、ぼくが何故こんなにたくさんの人からプレゼントをもらっていたのかも知らずにぼくに会いに来たんじゃない? 今日はね、ぼくの誕生日なんだ。でも、もう少しで『今日』も過ぎてしまう……そんな気がする。そしたらあなたともお別れをしなくちゃいけない。」 そう言って小さくため息をついたジョシュアは、自分でそのことに驚いた。残念そうにため息をつくなんて――目の前にいるこの人とお別れをすることを寂しく思うなんて、彼にとって意外だったからだ。 目の前にいる人は、自分にとても近い感じがする。どこかで会ったような、よく知っているような……。その不思議な懐かしさのためだろうか、だから自分は急にこんなにおしゃべりになったのか、と思い、誰かとの別れを惜しむという感情を抱くことがあるなんて思いもしなかったと内心で呟きながら、ジョシュアは試すようにこんなことを口にした。 「生まれた日をお祝いするという理由でプレゼントをあれこれたくさんもらったけど、たぶん明日になったら全部値打ちがなくなるよ。なのに、持ってくる。本当に大人って変だよね。たぶんぼくじゃなくて、ぼくのお父さんのために贈るプレゼントなんだよ。あなたは……どうかな? あなたなら、ぼくに何をくれるの?」 この問いに相手は少しの間黙って考えていたが、やがて「とても甘いもの。」と答えた。 「とても甘いもの……? なんだろう。甘いものと言えば大体お菓子とかキャンディ、そういうおやつかな? ぼくはあまり食べ物に執着しないけどね。ひもじい思いをしたことが無いからかもしれないけど……。」 そんな返答に、相手は困ったのか沈黙を返してきたが、ジョシュアは気にせず、「でも、」と言葉を続けた。 「甘いものってアイスクリームやお菓子だけじゃないもんね。たとえば言葉や時間、それだけじゃなく記憶や態度も……甘くなる場合があるんでしょ。たくさんの詩や歌がそう伝えているからね。だから世の中には甘い声も存在するし、甘い表情も存在する。今のぼくには全然理解できないけど……。いつかは理解できるようになったらいいな。」 ジョシュアのそんな答えに満足したのかどうかは判らないが、相手はにこりと笑って頷くと、ふいに彼の傍らに、服が汚れるのも気にせず膝をつく。そして、「誕生日おめでとう。」と言って子供の彼の手の平にのせてもすっぽりおさまるくらい小さな髪飾り――幸せクローバーを髪につけてくれた。 「あ……あれ? わ、これはさらに意外だね。ぼくにくれるの? 今までたくさんの誕生日プレゼントをもらってきたけど、こんなに意外だったのは初めてだよ。」 ジョシュアはそう言って嬉しそうに髪に飾られた小さな四つ葉のクローバーに触れた。 「ぼく、本当に困るほどたくさんのプレゼントをもらってきたから、これ以上はもういらないって思ってたの。別に無くても構わないと思ってたから。だから、何かをもらってこんなふうになったのは初めてだよ。」 「こんなふう……?」 不思議そうにくり返した相手に、ジョシュアは一つ頷いて「こんな気持ち……というか。」と呟いた。 しかし、相手はますます判らないというように眉を寄せてみせる。それを面白がるような楽しげな表情を浮かべて、ジョシュアは、「これってやっぱり夢なのかな? もう、夢でも夢じゃなくてもいいけどさ。」と笑った。 「夢って目覚めた後は思い出せないものらしいよ。ずっと憶えている夢もあるけど、ほとんどの夢は一日も経たないうちに全部忘れてしまうんだって。でも……ぼくは忘れない。たとえあなたがぼくに関することを全部忘れて、世界中の人があなたのことを忘れたとしても……ぼくはあなたのことを忘れないから。あなたの名前は知らないけど……今日のことは絶対に忘れない。そう考えてみると、プレゼントっていうのは『証』ということだね。」 確信に満ちた口調でジョシュアは言い、先ほど作った花の冠を、まだ傍らでかがんだままの相手の頭の上にのせた。 「いつかまたあなたに会った時、あなたはぼくのことを憶えているかな? ……きっと忘れてしまうだろうね。そう思うと寂しいよ。だからこれを受け取って。ぼくからのプレゼントだよ。プレゼントは証。証は記憶の足かせ……かもしれないけどね。」 子供らしからぬ皮肉っぽい口調で、しかし、同時におどけたような様子で笑って言う彼に、相手も微笑み返す。それを見ながら、ジョシュアは「それじゃ、ぼくはもう帰らなくちゃ。いきなりこんな所に来た分、いきなり帰るようになるんだね。さよなら。夢の中の来訪者さん。」と呟いた。 漠然と、もう帰らなければならないこと、また、ここにはもう来られないだろうことが判ったのだ。 別れはつらく名残惜しいが、たくさん時間をかけたからといって、いつまでも記憶に残るというわけではないことを彼は知っていた。刹那の出会いでも、永遠に記憶に刻まれることがある。つらい別れの方が、いつまでも思い出に残るものだと。 そうして彼は夢から覚めるように、その不思議な広場から抜け出したのだった。 「あら……意外ですわ。」 突然そんな声がかけられたのと、ジョシュアが回想から戻り目を開けたのはほぼ同時だった。凛としたその声でやってきたのが誰であるかすぐに判ったが、彼はまるで声の主を確かめるように振り返った。もしかしたら、その声の主こそあの時傍にいた人なのかもしれない、とでもいうように。 「こんにちは、クロエお嬢様。何がそんなに意外なのですか?」 彼はそう言って思った通りの声の主――クロエ・ダ・フォンティナに笑いかけた。 「こんなところにいらっしゃることも、そんな服装をしていらっしゃることも。……意外ですわ。」 「服装は……いつの間にかこうなりましたね。」 小さく肩をすくめてジョシュアが言うと、意味ありげな目を向けてクロエは唐突に話を変えた。 「昔、誕生日パーティが退屈でこちらに逃げてきたおぼっちゃまにお会いしたことがありますが、今日は幸いいらっしゃらないようですわ。」 「いつまでも子供でいることはできないから、そのおぼっちゃまも少しは成長したんでしょう。」 ジョシュアはそう答えながら、子供の頃に彼女に言われた言葉を思い出していた。確か小さなクロエ嬢は、「こんな所に隠れていたのですか、子供のように意地を張って人を困らせたりせず、お祝いに来てくれた人たちに子供らしく嬉しいふりをして差し上げるのが礼儀ですわ。」と彼をたしなめたのだ。 子供っぽいところを咎めた彼女は、同時に子供らしくあることを彼に説いたわけだが、今日の彼女はあの日と同じ理由で彼を叱る代わりに、 「それでもおぼっちゃまは格式高い服装をしておられたようですが。」 と、上質ではあるもののパーティにはあまり相応しくないジョシュアの服装に鋭く指摘を入れてから、小さく微笑んで「とにかく、」と言葉をついだ。 「今日はいらっしゃらないおぼっちゃまの代わりにこれを受け取ってください。あの時のおぼっちゃまなら、高い包装紙に包まれたプレゼントより、こちらの方が気に入ってくださるかもと思い、持ってきましたわ。」 クロエが差し出したのは、小さなかごいっぱいの白い木の実だ。メリーベリーという樹からとれるものの内、白い実はもっとも少なく、これほどの数を手に入れるのは難しい。その分、味は格別だ。 「確かにお渡ししておきます。そのおぼっちゃま……に。同じく退屈なパーティに飽きてしまい逃げ出したお嬢さんからのプレゼンだと伝えれば宜しいでしょうか?」 かごを受け取りながらジョシュアが言うと、クロエは口元だけで綺麗に笑ってみせる。 「とても面白いことを言いますわね。しかしアルニム家のおぼっちゃまは、意外につまらない生活を送っていらっしゃるようですわね。せっかくの誕生日なのに……静かに一日を過ごすのも良いですが、一緒にお祝いしたい人がいるなら今日が終わってしまう前に訪ねるのも良いのではないでしょうか。」 「ああ……普通はそうですね。」 ジョシュアがそう答えたきり黙りこんでしまうと、クロエはやれやれというように上品に咳払いを一つし、 「それでは、おせっかいもここまでにしておきますわ。わたくしはこれで失礼します。余計なことに巻き込まれるのは遠慮したいですから。」 と言い置いて優雅に踵を返し、長い金色の髪を揺らせて去っていった。 そんな彼女の後姿を見送りながら、ジョシュアは苦々しく呟く。 「一緒にいたい人……か。クロエお嬢様、こちらこそ意外です。クロエお嬢様には一緒にお祝いする人がいるようですが、こちらはそんな状況ではないですから。……会いたいからといって、いつでも探し出せるなら悩みませんよ。」 ジョシュアはそう言って小さく息を吐き出した。もしやあの時、幸せクローバーをくれたのは、今は傍にいない古い友人だったろうかとも思うが、確信を得るには至らない。何しろ景色や交わした言葉は一語一句思い出せるのに、その人が何番目に訪れた人であるかも、浮かべた表情も憶えているのに、その姿、顔だけが思い出せないのだ。そして、そのことが彼には不思議でならなかった。 「この幸せクローバーは一体誰から受け取ったのだろう? フォンティナ家のお嬢様ではなかったかと思うが……他の誰かのような気もする。……あなたがくれたのでもないだろうし。そうだろう?」 まるで言葉を空に放り投げるようにして言ったジョシュアの視線の先に、突然ふわりと音もなく少女が現れる。白いスカートをはためかせ、彼女は天使が落とした一枚の羽のように宙に漂いながらしばらくの沈黙の後、こう答えた。 「記憶というのは溜まって、重なって、入り乱れるものだから。時間も空間もいくつかの層に重なっているもの。どんなことも単独で存在することはできない。全ての記憶も全ての存在も、『選択』の結果だから。」 「ではオレはこの幸せクローバーを受け取った記憶を選択したということ? これを受け取った『オレ』には、一緒に祝って、プレゼントを交換するほどの相手がいたということだろう? まさに意外だけど。」 自分のことを他人のように客観的に言うジョシュアを、少女は礼儀正しい沈黙を守って静かに見ている。 まるで選び取ったかのようにたった一つ抜け落ちた記憶。それはもしかしたら、まさしく忘れられることを望まれ、そして、それを選択した結果なのかもしれない。 だが、すべてを彼は忘れてしまったわけではなかった。ちっぽけな髪飾りを手にした途端によみがえった思い出は、誰かからプレゼントをもらったという記憶は、ただ一つのことをのぞいて昨日のことのように細部にわたって鮮明だったのだから。 大事な思い出は、決して失われてはいない。 それがはっきりと判るとジョシュアは明るい表情で、空をただよっている少女を見やり、こう告げた。 「とにかく今現在これがオレの掌にあって、オレは確かにこの幸せクローバーを憶えている。今はそれでいいだろう?」 これに彼女は静かに頷き返す。 「ええ。それでいいわ。選択して……そして見つけて。あなたがしなければならないことを。あなたたちの古い記憶を……。」 少女はそう言うと現れた時同様に音もなく、明るい日差しに溶け込むようにして去っていった。 再び一人になったジョシュアは、もう一度心の中で「それでいい。」と呟き、髪を飾っている小さなクローバーに触れる。 あの人がくれたのは、幸せクローバーだけではなかった。ジョシュアのために費やされた時間。それも彼に贈られたかけがえのないものだ。何故なら、その人と話しているうちに、いつの間にか彼の心から、はじめに感じていたあの不安や困惑、焦燥に似た心地よいとは言い難い奇妙な気分が消えてなくなっていたのだから。 「プレゼントは証。だから、思い出せなくても今は構わない。この幸せクローバーが、確かにあれは夢でなく現実であったと証明してくれる。そして、少なくともオレはこの証を記憶の足かせだとは思わないから。」 ジョシュアは心の中で呟いて、かごの中からホワイトベリーを一つ手に取り、口に放り込んだ。それはとても甘く、どこか優しい春の味に似ていたかもしれない。 Fin. clap? |
| .......................................................................................................................................................................................................................................... |
| ▼コメント 題名の意味は「望まれた忘却」という意味でつけましたが、「忘却」にあてた「limbo」という単語には「辺獄、拘留所、刑務所、監獄、拘禁」という意味もあるのだそうです。ジョシュアの言っていた「記憶の足かせ」となりうるかどうか、という点でちょっと意味深な感じになったので、この単語を使いました(「忘却」の意味が薄れていそうですけども)。 しかし、英作にはあまり自信がないので、変な英語だったらすみません。 不穏な題名になりましたが、ジョシュアにとっては良き思い出になっていることを祈ります。 何はともあれ、お誕生日おめでとう、ジョシュア。 あなたが永遠に変わらないことが、わたしにとっては救いです。 |
| .......................................................................................................................................................................................................................................... |
主催サイト様: HisTales ホーム: |
| .......................................................................................................................................................................................................................................... |
BACK |
 |
 |
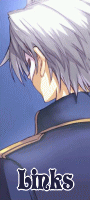 |