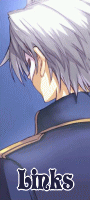| .......................................................................................................................................................................................................................................... |
| このお話は、例によってジョシュアの誕生日を祝し、私Hursaの妄想によって制作されたオリジナルの短編です。 いつもジョシュアと一緒にいる背後霊にちょっと人格がついておりますので、もしイメージを壊してしまったらすみません。 いちファンの一見解だと思って見逃していただければ幸いです。 何はともあれ、毎年(内容がくだらないにしても)こうしてお祝いできる幸せが少しでも伝われば嬉しいです。 ジョシュア、誕生日おめでとう! Hursa |
| .......................................................................................................................................................................................................................................... |
| 誰かが生まれた日にはお祝いをするらしい。その人がやがて赤ん坊ではなくなり、はうのをやめて立って歩くようになり、そして大人になり老人になっても、何度でも人はその日生まれた誰かに「おめでとう」の言葉をくり返す。それが特に親しい相手なら、贈り物もそえて。 その習慣が、生きている人間の間ではさして珍しいものではないことを「それ」はすっかり忘れていた。何しろ「それ」は人に祝いの言葉を告げるための肉声を失ってずいぶんとたつし、贈り物を運ぶための手もとっくになくしてしまっていたからだ。 長い間、「それ」が傍にいることに注意を払う者はいなかった。 ふらふらと町や村の中をただよっている「それ」に向けて、ごくまれに薄気味悪そうに視線を向ける者もいたが、彼らは決まってすぐに目をそらし、「それ」がそこに存在していないかのような顔をして足早に立ち去ってしまう。あとを追いかけて手をふってみても、向こうの景色が透けて見えている「それ」に手をふり返してくれる人はいなかった。 そのことをさみしいと思わなくなったのはいつからだろう? 「それ」はあまりにも誰にも相手にされないので、次第に怒りっぽくなり、自分の存在にうっすらと感づく人々に手当たり次第に近づいてはいたずらをして気を晴らすようになった。 いたずらに驚いて皆が逃げ出すのを見るのは愉快だったし、叱る者もいない。「それ」はいたずらに没頭して、そのうちにさみしさも忘れてしまった。 しかし、何か別の忘れてはいけないものまでどこかへ落っことしてしまったのではないかと気づいたのは、最近のことだ。 彼に会ったからだ、と「それ」は思った。 ある日、太陽ではなくベイラスとシエナ、二つの月が見下ろす夜の町で、「それ」は気配に気づいてちらと自分の方へ顔を向けた少年と目が合った――ように思った。そういう人間は「それ」のかっこうの標的だ。 そこで「それ」は、背を向けて一人で歩いていくその少年に後ろから近づき、おどかしてやろうといつものように相手の肩をたたいた。そして、彼がふり返ったところでとびきりの恐ろしい顔をしてみせる。 ところが――。 「ははは」 少年はおびえるどころか快活に笑うと、こともあろうに「その顔、お化けらしくてとてもいいね」と「それ」をほめたばかりか、「ありがとう」と言いさえしたので、「それ」はすっかり驚き、また拍子抜けしてしまって、姿を消すのも忘れ呆然とその場に立ちつくしてしまった。 そんな「それ」に少年が、 「オレはこれまでいろんな人から、それはいろんな贈り物をもらったけど、こんなに素晴らしいタイミングでこんなに気の利いたものをもらったのは初めてだよ」 と言う。それから、ますます訳が判らないといった困惑顔で首をかしげる「それ」に、「今日はオレの誕生日なんだ」と付け足した。 「実はもうすぐブルーコーラルという町で、ホラーアトラクションの新設記念に、幽霊がたくさん出る劇を上演する予定でね。オレもその幽霊役の一人として出るんだけど、幽霊をどう演じればいいのか判らなくてずっと困ってたんだ。それでまあ、こんな時間まで眠れずにうろうろしていたんだけど……そうしたら、さっきあなたと目が合っただろう? それでオレは、あなたがオレを怖い顔でおどかしてくれやしないかと思ったんだ。本当のお化けがどんなおどかし方をするのか知りたかったから。そしたら何と、本当にその願いが叶ったというわけさ」 少年はそう言ってにこりと笑うと、 「あなたが演劇に興味があるかどうか判らないけど、もし良かったら舞台を見に来てよ。きっと本物のあなたも感心するような演技をしてみせるから。お化け役がうまい俳優を見かけたら、どんな衣装を身にまとっていてもそれはオレだと思ってくれていいよ」 と、まるで親しい友人にでも話すようにして、「それじゃあ、もう帰って休まなくちゃ」と「それ」に手をふり、すたすたと歩き出す。 「それ」はかなりの長い時を「お化け」として過ごしていたが、いたずらに失敗したのも、お礼を言われたのもこの時が初めてだった。 だから――あまりにもびっくりしすぎたせいだろうか。「それ」は気がつけばふらふらと少年のあとを追いかけていた。 そしてもう一度、少年の肩をたたく。「それ」は声のかけかたを忘れていたので、相手の気を引く方法がそれしか判らなかった。 とんとん、と指のない手で肩をつつかれ、彼は再度ふり返る。 その顔が先ほどの「それ」に負けないくらいの恐ろしい形相だったので、「それ」は驚いてさっと隠れてしまった。 「ははは」 人気のない夜の町に、また少年の笑い声が心地良く響く。 「確かにこれは……人をおどかすのは結構楽しいけど、ずっと怖がられるのはオレはごめんだな。オレは俳優だから、時には観客を怖がらせる演技もするけど、悲鳴より拍手をもらう方がいいや」 そう言って少年は姿の見えなくなった「それ」を探して周囲を見回したが、相手が出てくる気配がないと悟り、やがて小さくため息をついた。 「あなたはたぶん俳優じゃないだろうから、オレとは意見が違うかもしれないけど、怖がらせる役ばかり好んでやることはないんじゃないかな。誰かがあなたにその役をやれと言った訳じゃないなら――いや、たとえそうであったとしても、役は選ぶべきだよ。さみしいのが嫌いならね」 それだけ言うと少年は再び歩き出し、ふり返ることなく立ち去ってしまった。 それから間もなく、本当に幽霊ばかりが登場する劇がブルーコーラルの新アトラクション、「恐怖の家」で上演された。普段からお祭り騒ぎの町はいっそうにぎわい、店はどこもかしこも大入りだ。 もっとも、「恐怖の家」のマスコットキャラクターであるファウスティーノをかたどった人形を並べている土産物屋の一角だけは閑散としていたのだが。 どうやらファウスティーノのつけているホラーマスクが不気味だと不評らしい。土産物屋は初日でその人形を店先に並べるのをやめてしまったから、それを買った者はとても少ないだろう。 そんな経緯を見守っていた「それ」は、みんなお化けの良さを判っていないな、と思った。 そう、「それ」はあの少年がどんな幽霊を演じるのか見てやろうと思い、こっそりとブルーコーラルまでやって来ていたのだ。そして気がつけば、すべての公演を見てしまっていたのである。 舞台は大成功だった。特にあの少年が演じていた幽霊の王は(幽霊なのに)ひときわ存在感があり、恐ろしく、また同時に魅力的で、とりこにならなかった観客など一人もいない。確かに彼は他の誰よりもお化けの演技がうまかった。お化け以外にお化けのことをよく判っているのは彼だけだろうと「それ」が思ったほどだ。 みんなが彼を絶賛し、様々な言葉をかけては、去っていった。 彼の傍に残ったのは「それ」だけだ。 もともと一つの劇団に所属しているわけではなく、何か目的があって旅をしているらしい少年は、特別に親しい友人を作る風でもなく各地を転々としている。そんな彼のあとを追って「それ」もどこまでもついていった。 彼に会ってから、「それ」は何となくいたずらをするのがばからしくなってしまったのだ。 いや、正確には人をおどかして怖がらせることが楽しくなくなってしまった。一度失敗したことを続けるのはつまらないと思ったからだが、たぶん理由はそれだけではないだろう。「それ」は俳優ではなかったが、少年が言うようにさみしいのは嫌いだったから。 あるいは、「それ」も彼の演技に魅せられた者の一人かもしれない。 「それ」がついて来ていることに彼もそのうち気づいたが、追い払うつもりはないようだった。時々肩をたたかれてはふり返り、さっと隠れてしまう「それ」の片鱗を見て肩をすくめるだけだ。 そうして、つかず離れずといった距離で「それ」は彼の周辺をただよい、やがて一年が過ぎようとしていた。 その頃になって、「それ」は誕生日を祝うという人間の習慣を思い出したのだ。 少年と出会った日、彼はその日が自分の誕生日だと言った。それからもうすぐ一年がたつ。 「それ」は彼の誕生日を祝いたいと思った。 しかし、「それ」にはおめでとうを告げる声もなければ贈り物を渡す手もない。きっと他にも何か足りないものがあるだろうと「それ」は思ったが、だからといってあきらめきれなかった。 たぶんあの日のようにありがとうと言って欲しいだけなのだろう、と「それ」は思う。他にそんなことを「それ」に言ってくれる者は誰もいなかったから。 だから「それ」は自分にできること、彼に贈れるものを探し――そして、ようやく一つ見つけたのだ。 そろそろ眠ろうかと宿屋の部屋で一人ぼんやりと考えていたジョシュアは、ふいにとんとん、と肩をつつかれ、背後に顔を向けた。いつもならそこには誰の姿もないはずである。それでも彼は必ず肩をたたかれたらふり向いたし、かといってそのあとに特に何かを期待したこともない。 だが、何故か今日は一人のお化けが隠れもせずに立っていた。そして、ついてこい、とでもいうように手招きをしてするりと部屋の扉をくぐり抜けていく。 ジョシュアは何だろうと首をかしげながらもそのあとについて部屋を出ると、夜の町へ足を踏み出した。 ふわふわと宙をただよう幽霊を追い、そうしてたどりついたのは、町でもひときわ大きな貴族の邸宅である。幽霊はその屋敷のへいの上に浮かんでジョシュアを見下ろしていた。 「そこまで登れって言うのか?」 そう尋ねると、相手は無言のままにうなずく。 ジョシュアは少しの間ためらっていたが、やがてへいをぐるりとまわり、人通りのない横手からへいによじ登り始めた。 「お化けは気にしないかもしれないけど、一応、言っておくと、人間がこんな、ことをして、いるのを、見られたら、まずいんだ、よっと」 最後は体をへいの上に持ち上げるかけ声に変わったが、何にせよ案内人は彼の言葉を聞くつもりはないようだった。ただ黙然と、彼の背後を指さす。 ジョシュアはそれにつられるように後ろをふり返った。ちょうど小さな家についた窓が正面に見える。そこにはカーテンがかかっていたが、窓際には一つの人形がこちらに向けて置かれていた。それはホラーマスクをかぶり、ずんぐりとした体型をしている。ブルーコーラルでたった一日だけ売られていた大不評のあのファウスティーノの人形だ。 ジョシュアはその人形のことを知っていた。こんなものを買う人がいるのだろうかと、舞台が始まる前に土産物屋の前で見かけて思ったものである(彼は確かにお化けの演技はうまかったが、お化けと同じ好みというわけではなかったのだ)。 そして彼の懸念通り、翌日には店先からその人形はなくなっていた。店主は今ここでしか手に入らない限定品だと売り込んでいたようだったが、失敗に終わったらしい。 その人形のことは、あの舞台を見に来ていた者くらいしか知らないだろう。あの不人気ぶりからいって他のどこにも出回っている可能性がない。あの窓がある小さな家に住む人は、そんな物を買ったのだからよほどの変わり者なのだろう。 しかし、もちろん幽霊がジョシュアに知らせたかったのは、そんなことではなかった。 「そうか、あなたはあの舞台を見に来てくれたのか」 ジョシュアはそうつぶやいて、いつも近くをただよっている幽霊に目を向けた。 「人ではない人が来ている気配がしたから、もしかしたらと思ったけど……まさか本当に来てくれていたなんて、嬉しいよ。オレの演技は悪くなかったろう?」 その言葉に幽霊は一つうなずいてみせる。それから何か言いたそうにしたが、言葉が思いつかなかったのかはじめから話せないのか、何も言わなかった。 幽霊はそのことを残念に思っているらしい顔をしたが、ジョシュアは何となくすべて伝わったような気がしてにこりと笑いかけた。 「ありがとう。あなたにはまるでオレが何をもらうと嬉しいか、いつも判ってるみたいだ。俳優にとって賞賛は、観客からの何よりの贈り物だから」 彼のそんな言葉に「それ」は満足した。 そして、おや、と思う。何だか足りないものなどなかったようだ、と。「それ」には「おめでとう」を告げる声はなかったし「物」を贈る手もなかったが、「それ」が渡したかったものは彼にきちんと伝わったようだった。 彼は生きた人間なのに、「それ」には彼がどこか身近に感じられる。 俳優は舞台の上では誰にでもなれるが、逆に言えば舞台の上で演じているその「誰か」は、舞台の外では存在し得ない幽霊のようなものかもしれない。そして俳優は舞台を降りたら誰でもない、実体を持たない不定形な姿をしたお化けなのかもしれないと。だから傍にいて何となく居心地がいいのだろう、と「それ」は思った。 ジョシュアは演劇の舞台ではなく、ジョシュアとしての人生という舞台において、もう一人の自分を探しているが、それが彼にとって気が重い仕事であるのは、自分の幽霊――ドッペルゲンガーでも探しているような気になるからかもしれない。いくらお化けに慣れている彼でも、自分の幽霊を探すのは気が進まないようだ。 「それ」には彼をはげます声がないし、支える手もないが、何となく、まだ傍にいようと思った。何しろ幽霊に関しては「それ」の方がよほど経験豊かだ――いかに彼が幽霊を演じるのがうまいとしても。だから何かできることがあるかもしれないし、何もなかったとしても、たぶん彼は「それ」が近くにいてもさして気にしないだろう。せいぜい「あなたがいると、一人でいるよりは退屈じゃなくていいね」などと言うのが関の山だ。 そして、「それ」にはその言葉で充分だった。他にそんなことを「それ」に言う人は、やはりどこにもいないのだし、おどかして悲鳴をあげられるよりも笑って肩をすくめられる方が気分が良かったから。 Fin. clap? |
| .......................................................................................................................................................................................................................................... |